『欲望と幻想の市場 伝説の投機王リバモア』
人の飽くなき欲望と幻想が渦巻く市場。そこで4度の栄華と4度の破産を経験した男がいた。ジェシー・リバモア。20世紀初頭のアメリカで「ウォール街のグレートベア(大熊)」と恐れられた伝説の投機王である。エドウィン・ルフェーブルによって描かれた本書は、1923年に初版が刊行されて以来、投資家たちの必読書として今なお語り継がれている。単なる投資術の解説書ではない。一人の投機家の人生と相場哲学を通して、市場の本質と人間の心理を鮮やかに映し出す傑作だ。
波乱万丈の生涯と市場との戦い
マサチューセッツ州の貧しい家庭に生まれたリバモアは、14歳で家を飛び出し、株式仲買店で働き始める。黒板に株価を書く仕事をしながら、独自にティッカーテープを読み解く術を身につけていった。わずか15歳で初めての投機に成功。その後「無鉄砲な少年相場師」の異名を取るまでになる。
相場の世界に足を踏み入れたリバモアの人生は、まさに激動そのものだった。株式と商品相場で何度も巨万の富を築いては全てを失う。四度の破産と四度の復活。その度に市場から厳しい教訓を学び、自らの投資哲学を磨き上げていく。
特に1929年の世界恐慌では空売りを仕掛け、約1億ドル(現在の価値で約4000億円)という莫大な利益を手にする。しかしその結果、暴落の原因を作ったとして周囲から憎まれ、脅迫を受けるほどだった。相場の栄光と孤独。その両方を背負った男の姿が本書には生々しく描かれている。
時代を超える投資哲学の数々
「自分の判断が正しいと自信をもってゲームに臨む」「すべきではないことを学ぶ」「投機家の最大の敵は自分の中にある」「辛抱強く待つ」。リバモアが残した金言の数々は、今日の投資家にも強く響く言葉だ。
彼の投資手法は徹底した「順張り」を基本とし、相場全体の大きな流れを読むことを重視した。「上昇相場で買うのが最もスムーズな買いのタイミングだ」「株というものは、買い始めるのに高すぎるということはないし、売り始めるのに安すぎるということはない」。これらは現代の投資理論にも通じる洞察である。
特筆すべきは、リバモアが自ら体得した鉄則を破ったときに失敗していることだ。「他人の情報に耳を傾けるな」「他人のゲームに乗るな」「損切りを急いで利益を伸ばせ」「ナンピン買いをするな」「底打ちや天井を確かめる前に動くな」といった彼自身のルールを守れなかったとき、彼は大きな損失を被った。これは投資だけでなく、あらゆる決断においても普遍的な教訓ではないだろうか。
本質は変わらない―100年経った今も輝く洞察
驚くべきは、この本が初版から100年近く経った今でも色褪せない洞察に満ちていることだ。「1923年が初版とは思えないくらいに今の相場と類似点が多い。テクノロジー、法規則などは変わっても、人の感情はいつの時代も変わらない」。読者の感想にあるとおり、人間の心理や市場の本質は時を経ても変わらないという事実が、本書の価値を不変のものにしている。
もちろん、時代背景の違いはある。リバモアが活躍した時代は上場企業が数百社しかない市場黎明期であり、今では違法とされる株価操縦なども行われていた。しかし、そうした時代の制約を越えて、人間の欲望と恐怖が織りなす市場の本質を見抜いた点に、本書の真価がある。
投資書を超えた人生の教科書
本書の魅力は、単なる投資ノウハウの解説にとどまらない点だ。成功と挫折を繰り返した一人の人間の生き様を通して、人生の深遠な教訓を得ることができる。
リバモアは3度目の破産の際、すべての債権者に「再起したら必ず負債は返す」と約束して回り、実際に破産から2年後にすべての借金を返済した。こうした律儀さと強さが、彼の人間性の深みを物語っている。
しかし同時に、晩年はうつ病に苦しみ、最終的に自ら命を絶つという悲劇的な結末を迎えたことも見逃せない。市場で成功しても、内面の平安は別物であるという厳しい現実も、本書は教えてくれる。
熱狂と幻滅を繰り返す市場の真実
今やキーワードになってしまった「市場」は、投機家やディーラーだけで構成されているわけではない。わたしたち一人ひとりの欲望と幻想の総体、実はそれが「市場」の正体なのだ。
本書は表面的な投資テクニックではなく、市場の本質と向き合うための羅針盤を提供してくれる。100年前のアメリカで活躍した一人の投機家の姿を通して、私たちは時代を超えた市場の真実を垣間見ることができる。
「欲望と幻想の市場」。このタイトルこそが、本書の魅力を端的に表している。人間の飽くなき欲望と幻想が渦巻く市場で、私たちはどう立ち振る舞うべきか。リバモアの栄光と挫折の軌跡が、その答えのヒントを与えてくれるだろう。投資家はもちろん、人生の機微に関心を持つすべての人に、この一冊をぜひ手に取ってほしい。
※リンクはアフィリエイト広告です。お買い物でサイト運営を支援いただけます☕
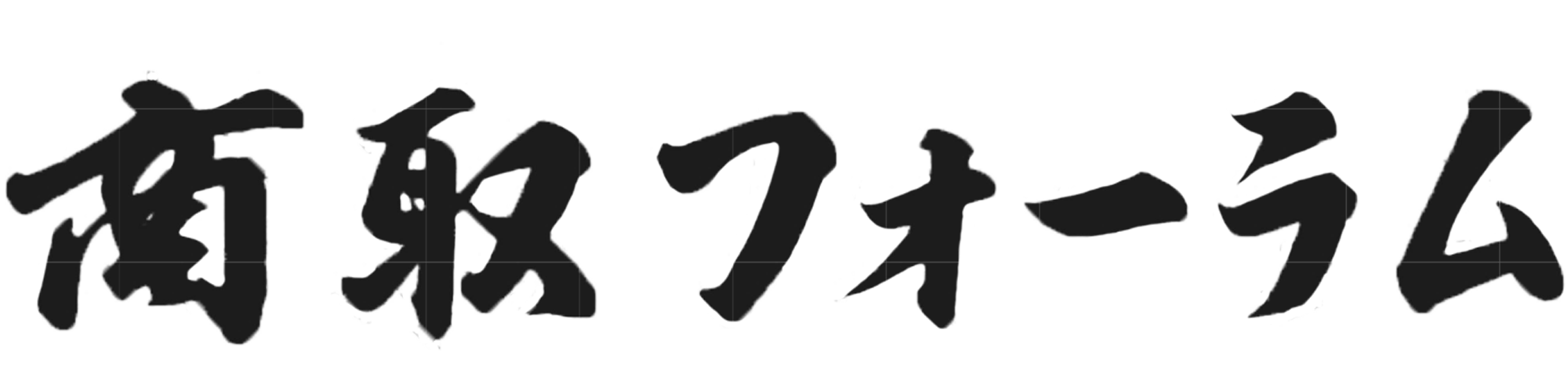
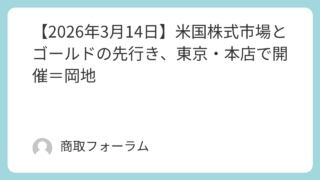
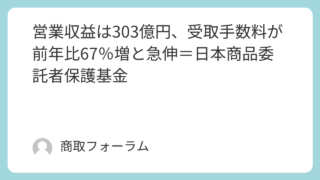
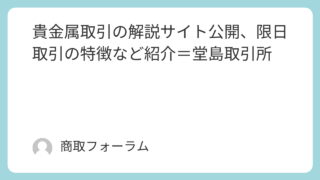
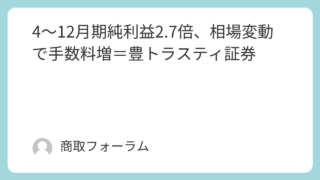
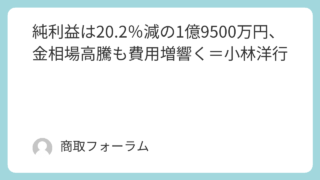
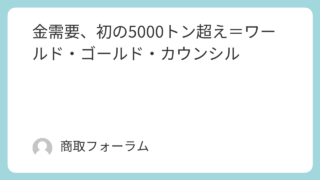
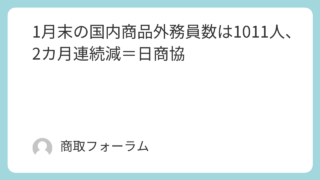
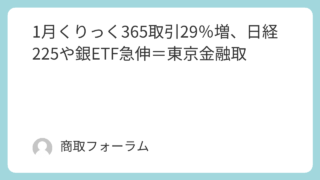
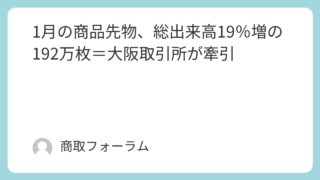
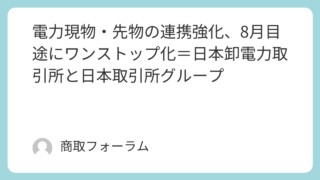
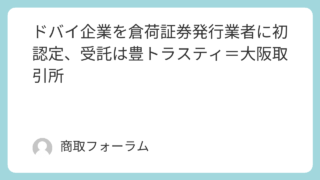
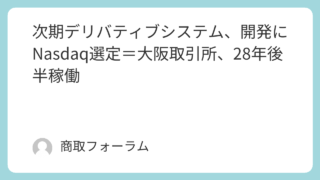
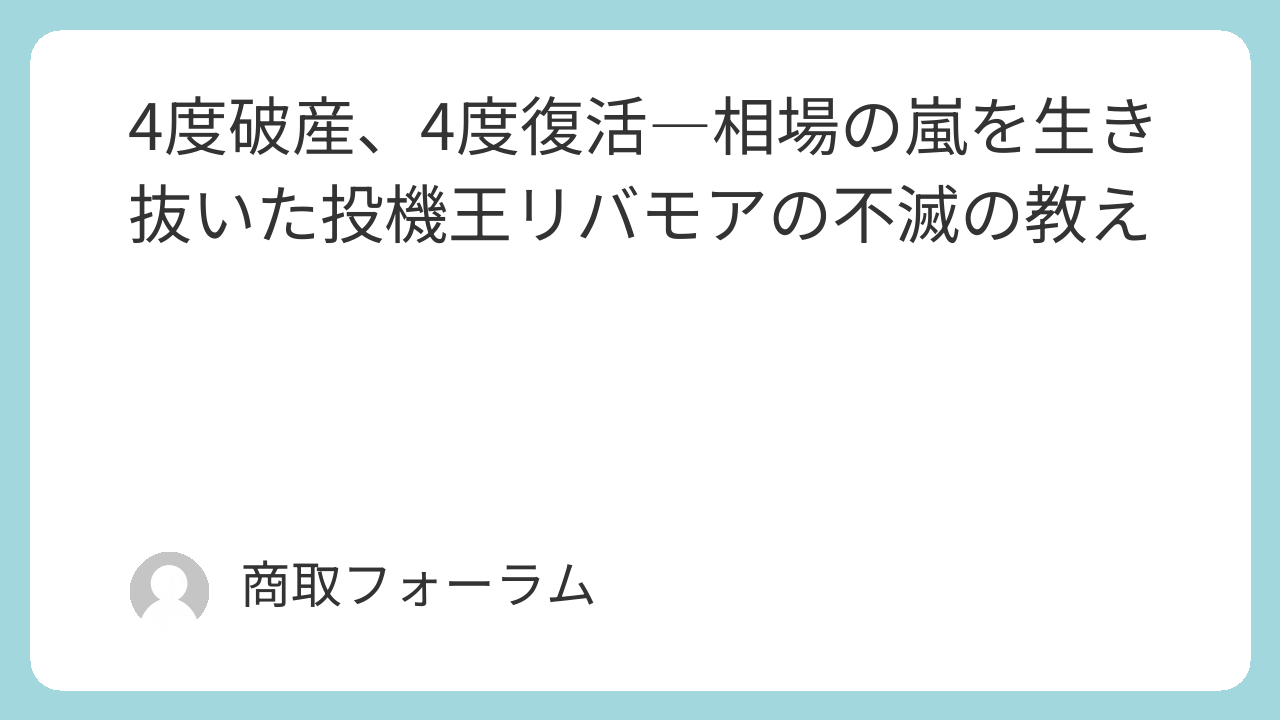
![欲望と幻想の市場 伝説の投機王リバモア [ エドウィン・ルフェーブル ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1114/9784492061114.jpg?_ex=128x128)