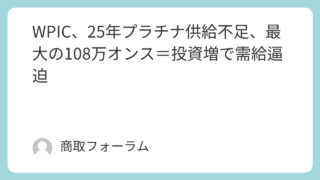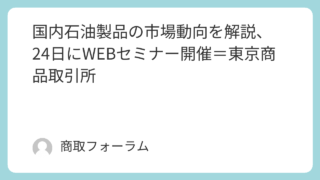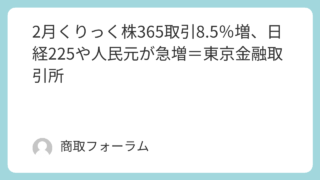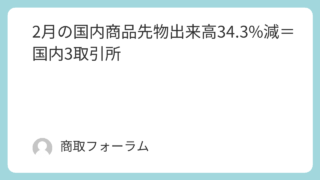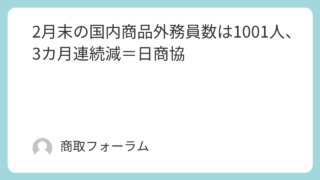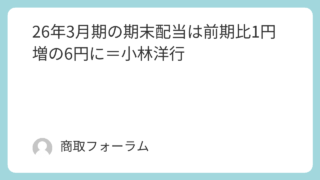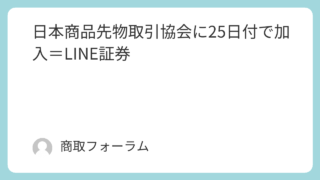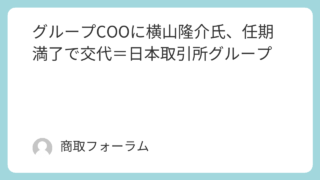歴史の始まりか終焉か
東京穀物商品取引所(渡辺好明社長)と東京工業品取引所(江崎格社長)は5月29、30日にそれぞれ臨時取締役会を開催し、来年2月をメドに東穀取の農産物市場のうち、トウモロコシ、一般大豆、小豆、粗糖の4品目を東工取に市場移管することを決定した。また、コメ(米穀)については関西商品取引所(岡本安明理事長)に移管する。今月末の株主総会で正式に決議されるが、同総会後に渡辺社長が辞任し、後任には現常務の畑野敬司氏を社長に選任する案が浮上している。新社長の下で市場移管を果たした後、来年中には会社整理(清算)され、1953年に再開されて以来60年余の歴史に幕を閉じることになる。
ドタバタ劇に決着
この結果、昨年7月に農水省が東穀、関西両商品取引所にコメの試験上場を認可することで始まった農産物市場の移管問題を巡るドタバタにようやく結着がつくことになった。この間の混乱は結局、事実上の経営破たんが明らかな東穀取の経営陣と農水省が、それでも「72年ぶりの再上場」という材料だけを奇貨にほとんど根拠のないまま、所詮は一民間企業でしかない自社の存続に拘泥したことによってもたらされたものだった。そもそも、東穀取の農産物市場移管は一昨年7月に、日本商品先物振興協会(加藤雅一会長=当時)が市場消失への危機感から東工取へ承継させるとともに、取引所自体の解散をも含めた提言を行ったことに端を発したものだった。同提言はコメ上場に起死回生をかけていた東穀取に一蹴される格好となったうえ、その後、東穀取自身が東工取に市場移管を申し入れた挙句、コメ上場認可でふたたび自らがそれを撤回するという、当たり前の企業経営ではおよそ考えられないテイタラクが演じられたのは周知の通り。
そもそも、明治以来の歴史と伝統によって日本の商品先物取引(と市場)のシンボルであった取引所の土地と建物(ビル)の売却そのものの経営判断の是非すら問われるところではあるが、一方でそれは取引所を株式会社化した時点で不可避のことだったのかもしれない。市場移管問題も、その端緒は縮小するマーケットとシステムや市場参加に伴うコスト軽減を求める先物協会による所管を越えた取引所統合(再編)に向けた提言にあった。もっとも、これについては文字通り、歴史も伝統も異なる背景と企業文化を無視した統合論に疑義を呈する声もあったが、いまとなっては、法改正(商品先物取引法施行)を含めた怒涛のごとき過剰規制行政による市場破壊のひとコマとなって、結局は東穀取の消滅という結果を招いた格好である。
移管だけでは不足
これもまた、業界の悲喜劇の一断面ということになるのであろうが、本来なら日本の商品先物の本流中の本流である東穀取と、それゆえ業界の王道でもあった農産物市場がこれによってその命脈を堅持できるか否かは全く別問題であるのはいうまでもない。「危殆に瀕している商取業界の重荷を一身に背負って立つ」 (多々良義成豊商事相談役)金によって、国内市場はかろうじて存続、維持されているといっても過言ではない。その意味では、移管先の東工取白身が経営的に崖っ縁にあり、農産物市場の再生とそれによるマーケット全体のポリュウム拡大には何らの保証もないのが実態である。
また、コメが移管されることになる関西取に、異なる商品設計による二つのコメ市場が並存するのか否かを含めて、関西米穀が残りの試験上場期間のうちに本上場へ向けた参加者拡大と社会への浸透やアピールを実現できるかは全く予断を許さないものがある。卸業者などによる受渡し実績を重ねることによって、農協ベースによる流通に風穴を開けつつあることは事実であるが、それがそのまま、ガソリン、灯油の石油市場並みかあるいはそれ以上の現物調達先としての取引所取引に成長できるかは、やはり、潤沢な一般投機玉(委託玉)を背景とする流動性の拡大いかんにかかるという基本的な課題(テーマ)にぶつかってしまう。
多様性こそ命綱
産構審商取分科会は今月の会合で事実上の取りまとめを行うスケジュールとなっている。あまりにも冷え込み、衰退してしまった国内商品先物市場の現実を前にして、取引所の存続うんぬんの以前に、このままでは旧取引員各社の事業意欲そのものが枯渇しかねない事態に直面している。前述した金の孤軍奮闘も、さしもの国際市況の大上昇期にも一応のピリオドが打たれたことで、ここからの先行きについては不透明感が強まっていることは否めない。つまり、いつまでも〝金頼み″は効かないことを意味している。にわかに金の代役を求めることができる環境にはないが、世界の商品先物市場は金(貴金属)も非鉄金属も原油も、さらには穀物などの農産物も含めて、そのライン・アップに伴う循環物色が当たり前に機能している。国内では上場商品が減少の一途を辿っているが、それは産業インフラとしての拡充という政策と完全に逆行している。行政の猛省を促す所以である。