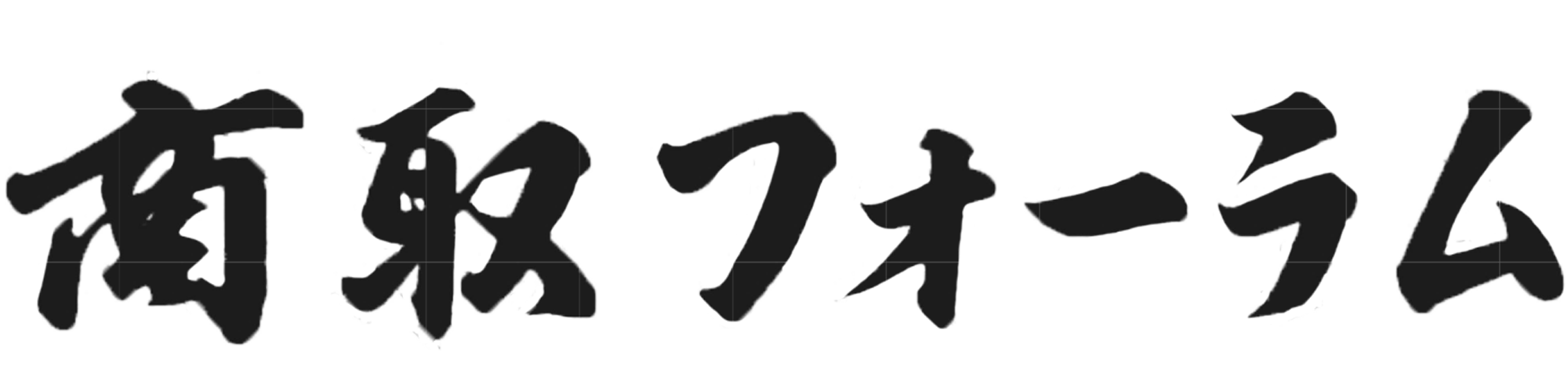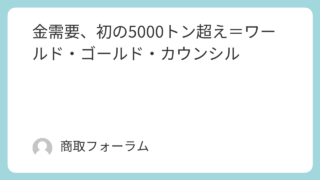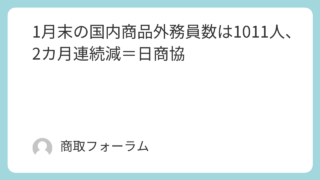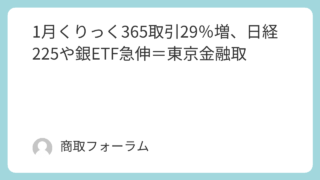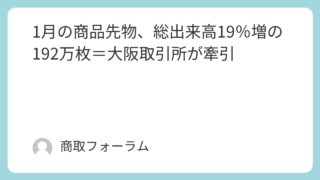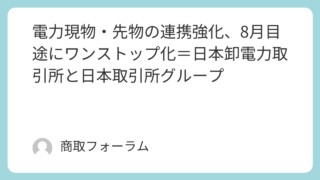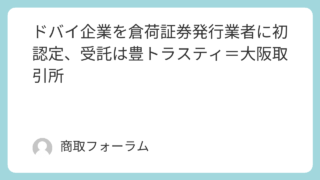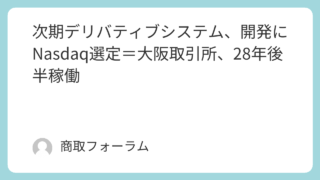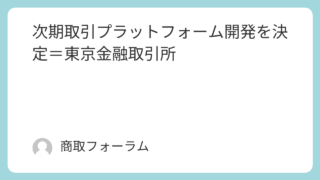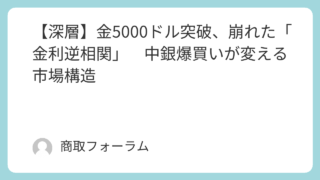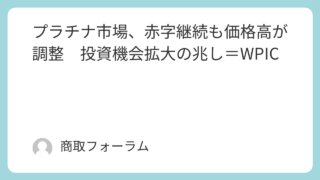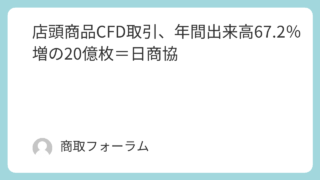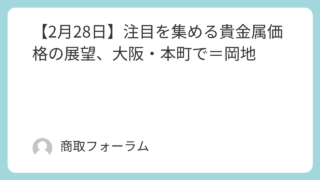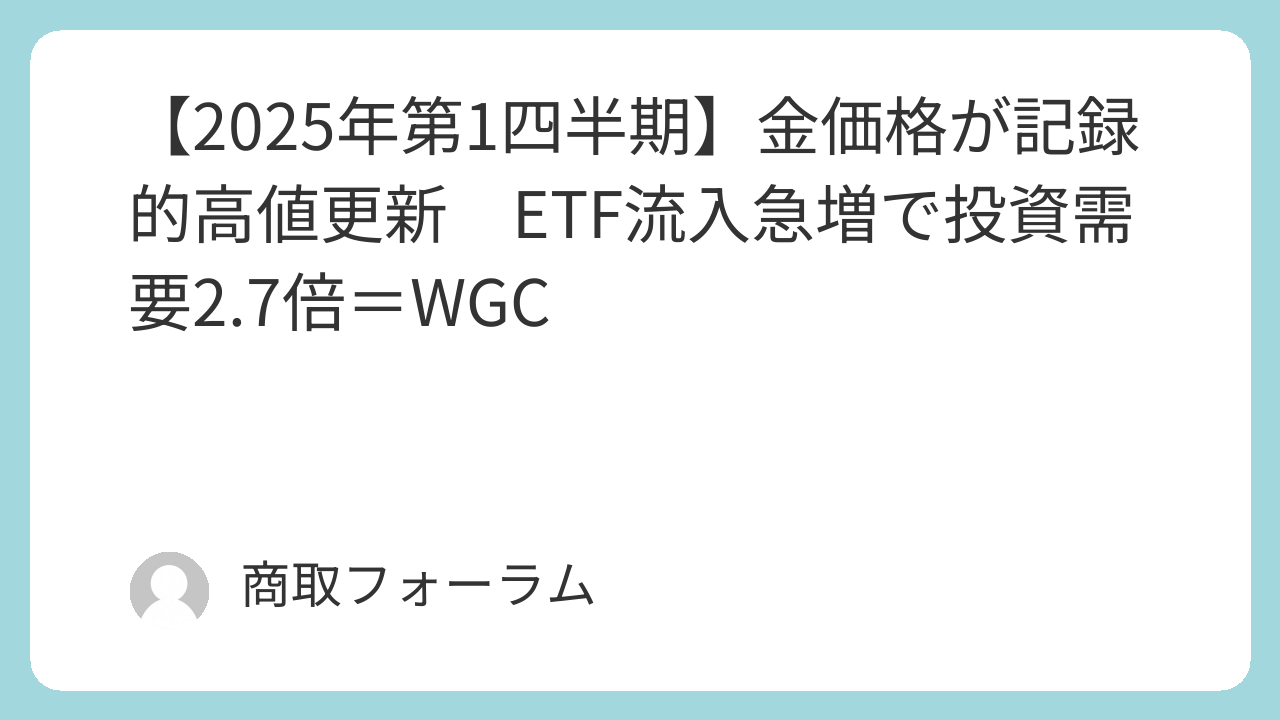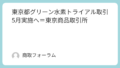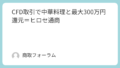ワールド・ゴールド・カウンシル(WGC)が発表した2025年第1四半期の金需要動向によると、金価格が記録的な高値を更新する中、ETF(上場投資信託)への資金流入が急増し、投資需要が前年同期比170%増と急拡大した。総需要は前年同期比1%増の1,206トンと2016年以降の第1四半期として最高水準となった。価格は四半期平均で1オンス2,860ドルと38%上昇。米国の関税政策、地政学的緊張、株式市場の変動などを背景に投資家の安全資産志向が強まっている。
金価格は今年に入って20回以上の最高値を更新。米国の不安定な関税政策発表や地政学的緊張の高まりなどを受け、1月から上昇基調が強まった。この価格上昇が投資家の関心を集め、さらなる資金流入を促す好循環を生んだ。
最も注目されるのは金ETFへの資金流入の急増だ。第1四半期のETFへの資金流入は226.5トンと、前年同期の113トンの流出から大幅に転換。投資需要全体は552トンと前年同期比2.7倍に拡大した。特に北米上場のETFが134トンと最大の流入を記録。欧州上場も55トン、アジア上場も34トンと世界的な広がりを見せた。
中央銀行による金購入も高水準を維持している。第1四半期の中央銀行による金購入は244トンと、前四半期からは減少したものの、過去3年間の四半期平均の範囲内の強い需要を示した。ポーランド国立銀行が49トンと最大の買い手となり、中国人民銀行も13トン購入した。WGCは「不確実性の高まりが中央銀行の金への関心を強めている」と分析する。
個人投資家の金地金・コイン需要も堅調だ。第1四半期の需要は325トンと前年同期比3%増。特に中国が124トンと前年同期比12%増と顕著な伸びを示した。中国では、株式・債券など国内資産のパフォーマンス低迷もあり、安全資産として金への投資意欲が高まっている。
一方、宝飾品需要は価格上昇の影響を強く受けた。第1四半期の宝飾品需要は380トンと前年同期比21%減少。2020年のコロナ禍以来の低水準となった。特に中国の需要は125トンと32%減少し、インドも71トンと25%減少。消費者は高価格に対応するため、購入を見送るか、より軽量な商品を選ぶ傾向が強まっている。しかし、金額ベースでは9%増の350億ドルとなり、消費者が予算を広げて購入している状況が示された。
テクノロジーセクターの需要は80トンと前年同期から横ばい。AI関連の需要が電子部品の成長を支えたものの、今後の関税に関する不確実性が業界にとって課題となっている。
供給面では、鉱山生産が856トンと第1四半期としては過去最高を記録。総供給は前年同期比1%増の1,206トンとなった。一方、リサイクル金は価格上昇にもかかわらず1%減の345トン。消費者がさらなる価格上昇を見込んで売却を控えている傾向が見られる。
今後の見通しについて、WGCは「投資需要は、スタグフレーションリスク、米国の財政赤字拡大、地政学的緊張などにより引き続き拡大する見込み」とする一方、「宝飾品需要は高価格と世界経済の成長鈍化により弱含み」との見方を示した。
金市場の構造変化が鮮明に ― 投資資産としての地位確立
金の需給構造に大きな変化が生じている。宝飾品や実需を中心とした従来の「消費財」としての金から、投資家が積極的に保有する「金融資産」としての金へと、その位置づけが明確に変わりつつある。2025年第1四半期のデータはこの変化を如実に示している。
かつて金需要の最大項目だった宝飾品が21%減少する一方、投資需要は前年同期比2.7倍に跳ね上がった。特に注目すべきは金ETFの動向だ。前年同期には113トンの流出だったものが、今期は226.5トンの流入へと劇的に転換した。この背景には、米国の予測不能な関税政策や地政学的緊張の高まりがある。不確実性が増す環境下で、株式と債券の相関が高まり、これが金の分散投資効果への注目を高めている。
中央銀行による金購入も構造変化を示す重要な指標だ。四半期244トンという購入量は、過去3年間の高水準の範囲内にある。ポーランド国立銀行が49トン、中国人民銀行が13トンを購入するなど、主要国が外貨準備の多様化を進めている。これは米国債への依存度を下げる動きでもあり、ドル基軸の国際通貨体制への信頼低下を示唆している。
金価格の上昇は、市場参加者の行動にも変化をもたらしている。通常、価格上昇時にはリサイクル金の供給増加が見られるが、今期は予想に反して1%減少した。消費者がさらなる価格上昇を見込んで売却を控えるとともに、近い将来に売却可能な在庫が既に枯渇しつつあることを示している。
中国の動向も注目に値する。宝飾品需要が32%減少する一方で、金地金・コイン需要は12%増加した。中国国内の株式・債券市場の不振と米中貿易摩擦の高まりにより、中国投資家が安全資産として金を選好している証左だ。
今後の金市場を展望すると、スタグフレーションリスクや米国の財政赤字拡大、地政学的緊張など、金需要を押し上げる要因は引き続き存在する。一方で、記録的な高値は宝飾品などの実需を抑制するため、金価格の上昇ペースは鈍化する可能性もある。
しかし長期的には、中央銀行による金保有比率の引き上げや、機関投資家のポートフォリオ分散ニーズの高まりが、金市場の構造変化を一段と進める可能性が高い。金はもはや単なる商品ではなく、グローバル金融システムの中で重要な役割を担う戦略的資産となりつつある。不確実性の時代において、金の価値は再評価されつつあるのだ。