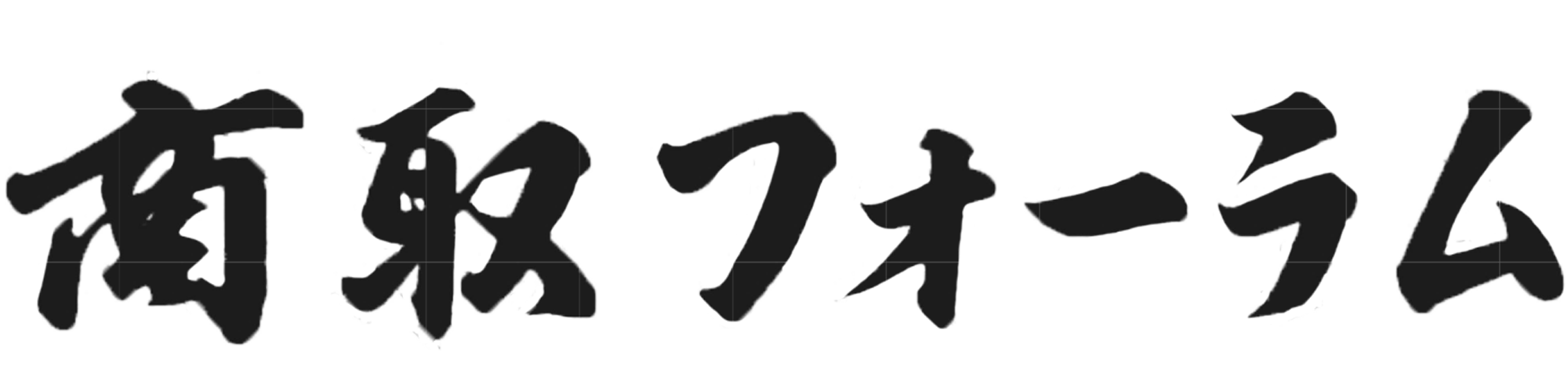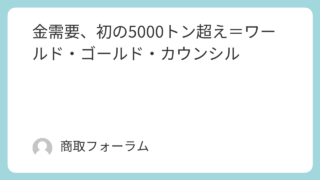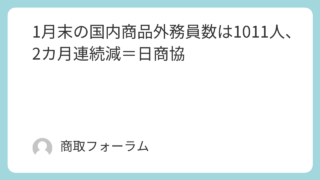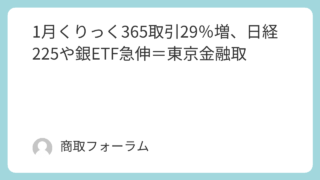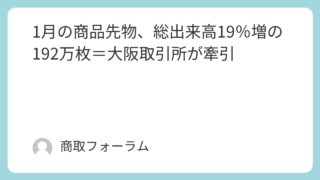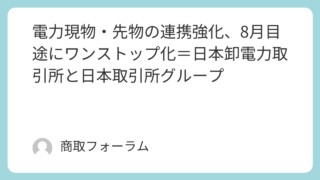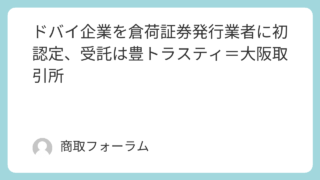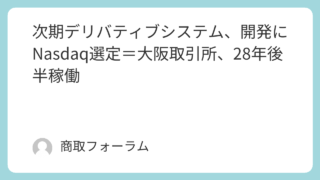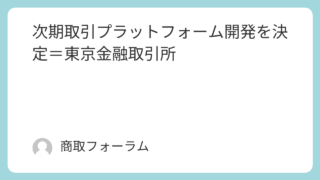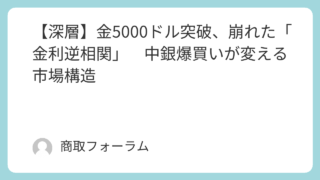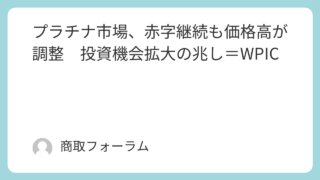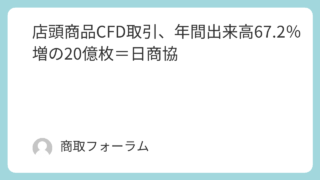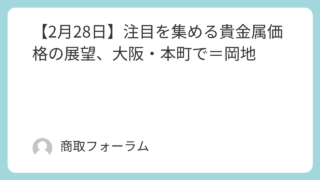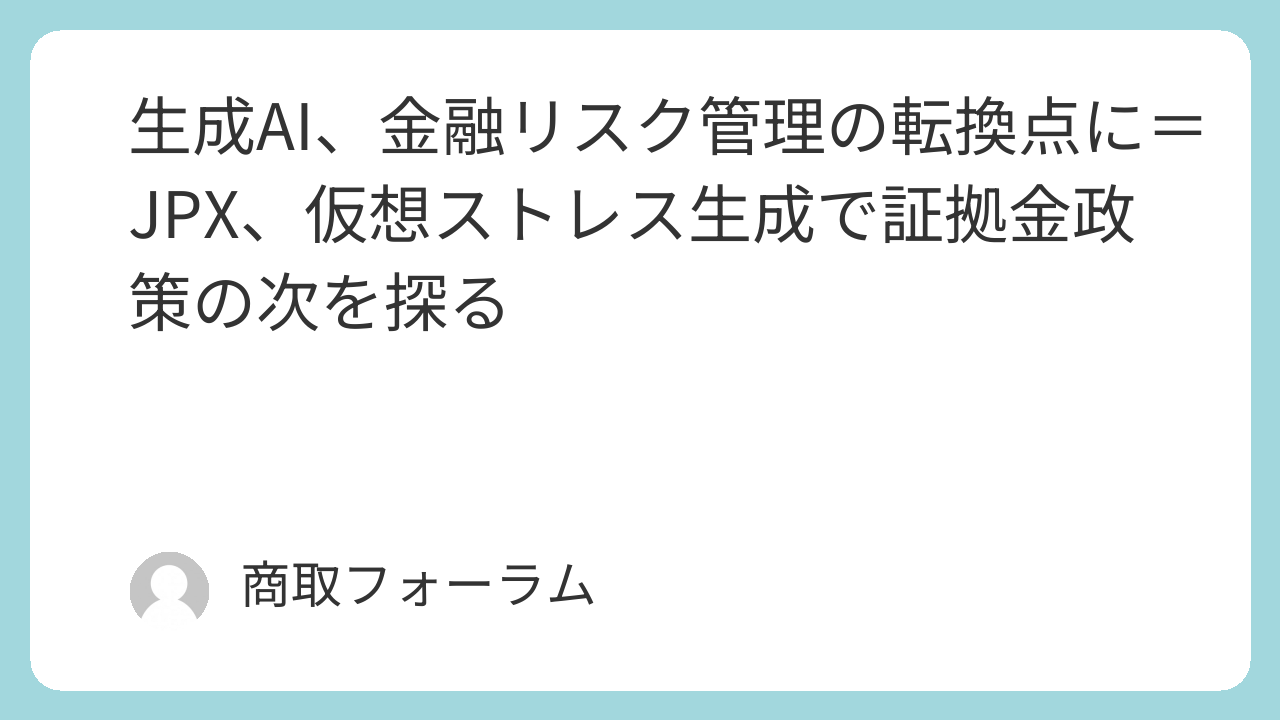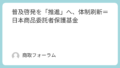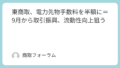日本取引所グループ(JPX)は4日、生成AI技術を活用した新たなリスク計測手法に関するワーキング・ペーパーを公表した。市場関係者が待望した「未経験極端事象」の再現を目指し、清算機関JSCCでAIモデルを応用した仮想マーケットシナリオの生成実験を実施した。金融証券インフラの進化を象徴する試みであり、今後の証拠金・リスク管理の高度化議論を牽引するとみられる。
清算機関CCPの根本課題は、デリバティブ市場の巨大リスクを集約して破綻連鎖を防ぐことにある。各参加者から預る当初証拠金(IM)の算定基礎となる損失額は、通常“VaR”手法を使いヒストリカルデータで評価される。ただしこの方式では「過去に実際に観測された値動き」しか再現できないため、現実には“起こりうるが未体験”の極端リスク(仮想シナリオ)が網羅されない弱点を抱えていた。
ワーキング・ペーパーでは、AI(変分オートエンコーダー=VAE)と旧来の主成分分析(PCA)を比較し、TONA3M先物曲線の2日間リターンから合成データを生成。オリジナルのストレスパターンにAI/PCA生成シナリオを加え、証拠金規模や損失予測(ES-VaR)への影響を評価した。VAEは多次元リスクファクター間の非線形依存性を自動学習でき、より多様かつ極端な値動きを再現する。
その結果、証拠金額の推計に最大で3割増をもたらす仮想リスクシナリオが生まれた。特にネットポジションが0に近いカレンダースプレッド型など従来見落とされがちだった構造的リスクで、AI生成シナリオが新たな損失パターンを浮き彫りにした。過去事例に依存するPCA手法との差異は明確で、VAEによる合成データは従来型ストレステストの限界を打破する可能性を示唆する。
このアプローチは、単なる技術革新にとどまらない。極端シナリオを“ブラックボックス”なAIモデルから導出することは、「納得できる証拠金水準」の合意形成という現場課題に直面する。AIを資本規制や証拠金政策に応用する場合、説明責任や訓練データの信頼性確保、制度との整合性を巡る慎重な検証・調整が不可欠となる。
金融インフラの進化と資本効率改善の両立は相反しやすいが、非線形・複雑なマーケットリスクが増す現代において、「AIを味方につけるか」は今後の競争力を分ける分水嶺といえる。今後、JPXがGANや拡散モデルなど一層高度なAI技術導入を進めれば、リスク管理の信頼性・精緻化で新たな標準を打ち立てる可能性もある。一方、説明性の不足やデータ品質リスクの懸念は依然根強い。市場関係者はAIを巡る新たな技術リスクにも目を配りつつ、政策・制度設計への関与を強めるべきだ。
AIが切り拓く証拠金・リスク管理の未来。その実装には、技術的挑戦と制度的合意の二つを慎重に進める現実的視点が不可欠となる。市場の透明性と安定性維持の観点からも、議論の深まりが強く求められる段階を迎えている。