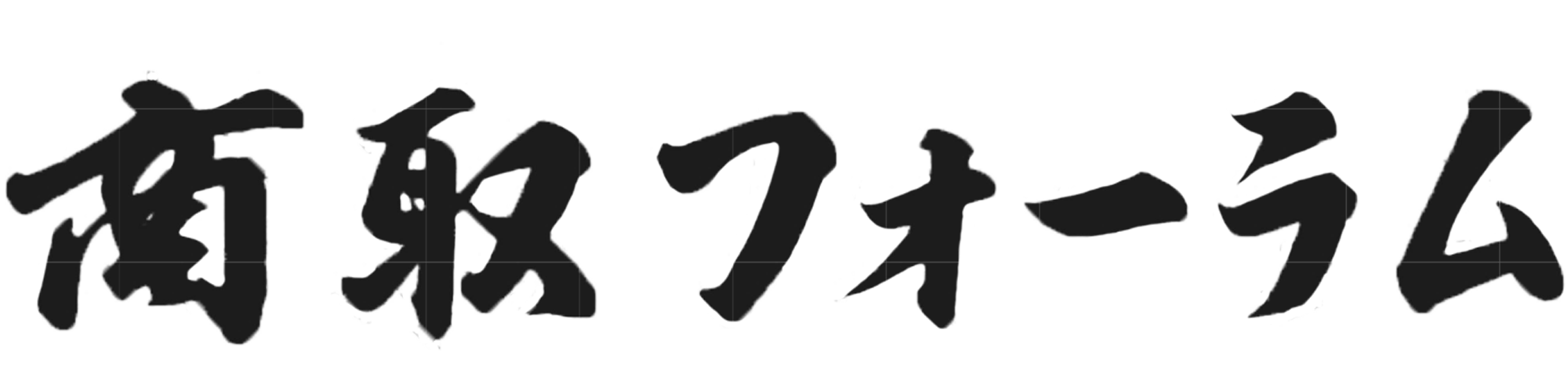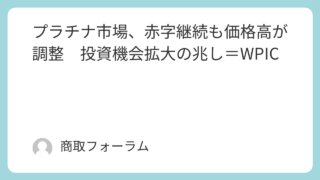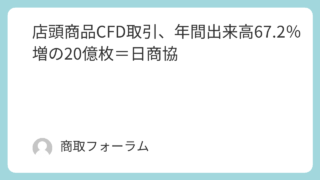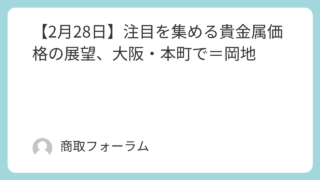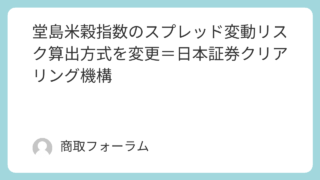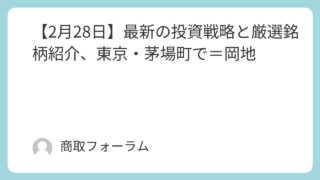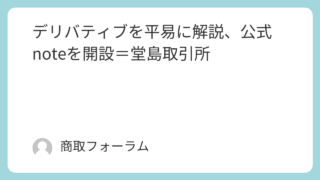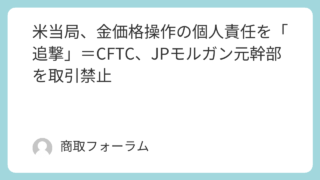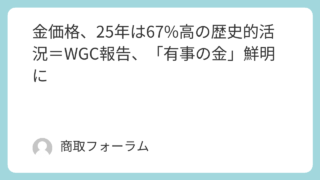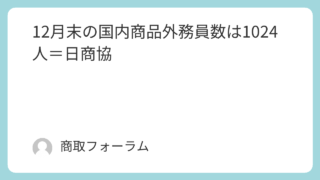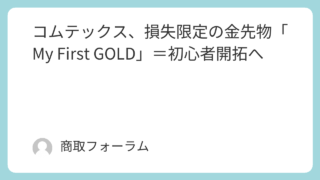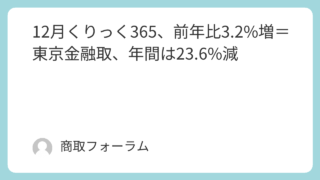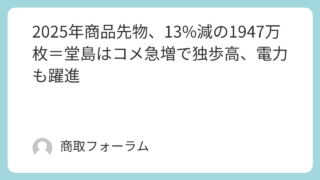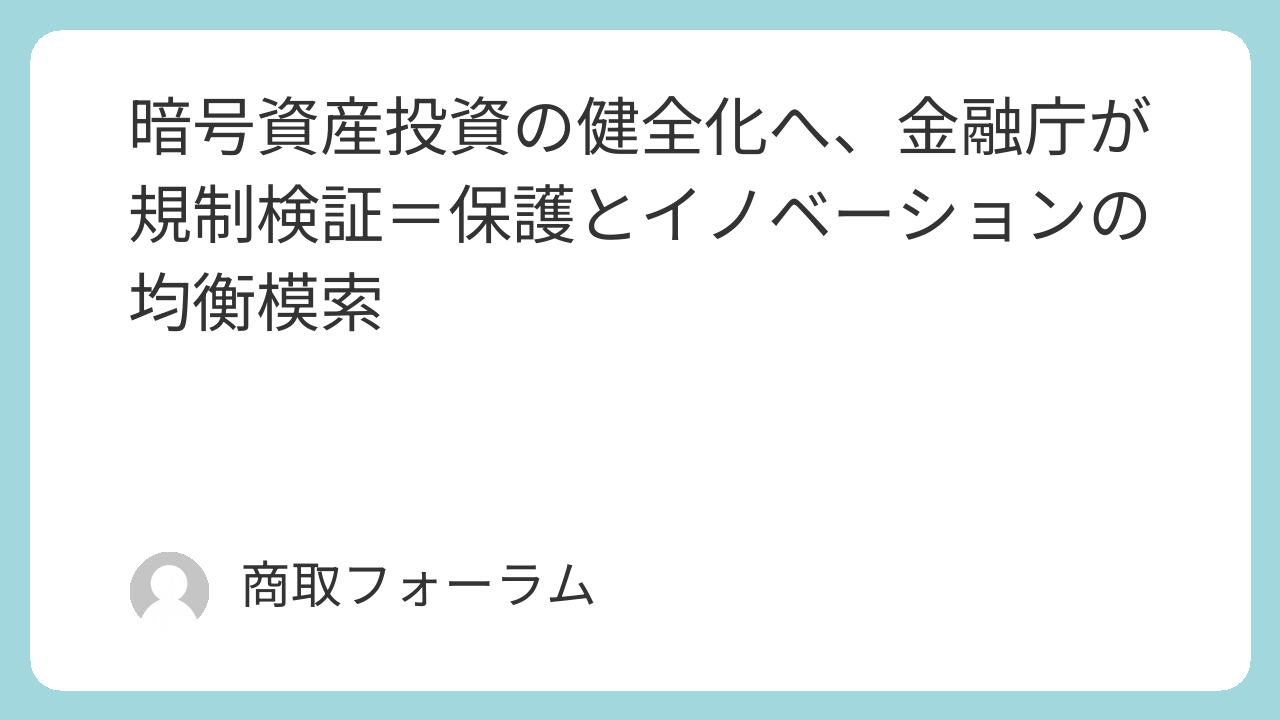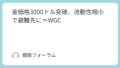金融庁は10日、暗号資産に関連する制度のあり方を検証したディスカッション・ペーパーを公表した。国内の暗号資産取引が活発化し、投資対象としての認知度が高まる一方で詐欺的な投資勧誘も横行する中、利用者保護とWeb3イノベーション促進の両立を目指す。発行者による情報開示強化やインサイダー取引規制の導入などを盛り込んだ制度見直しの方向性を示した。5月10日まで意見募集し、今後の具体的な規制改革に活かす方針だ。
暗号資産市場は2019年の法改正時から大きく様変わりした。国内では暗号資産交換業者における口座開設数が延べ1200万口座を超え、利用者預託金残高は5兆円以上に膨らんだ。投資経験者の暗号資産保有率は約7.3%と、FX取引や社債より高い数値を示している。米国ではビットコイン現物ETFに投資する機関投資家が1200社を超え、公的年金など長期保有を前提とする投資家も参入。投機の対象から正当な投資対象へと着実に位置づけが変化しているのだ。
金融庁が示した規制見直しの核心は、暗号資産を二つの類型に分けて対応する点にある。資金調達の手段として発行され、調達資金がプロジェクト運営などに利用される「資金調達・事業活動型」と、ビットコインやイーサなどの「非資金調達・非事業活動型」だ。この分類により、それぞれの特性に応じたきめ細かな規制設計が可能になる。
注目すべきは情報開示・提供規制の強化だ。資金調達型の暗号資産については、発行者に直接的な情報開示義務を課す方向性を示した。現状の自主規制ではホワイトペーパーの内容が不明確だったり、実際のコードと齟齬があったりする問題があるが、発行者自身に責任を持たせることで、情報の非対称性解消へと一歩前進する。非資金調達型については、交換業者に説明義務や重要情報の提供を求める案が示された。
業規制についても見直しが検討されている。暗号資産の投資セミナーやオンラインサロン等を通じた詐欺的行為が横行する中、無登録業者による違法な勧誘を抑止するためのより実効的な枠組みを整備する。また、暗号資産の投資運用・アドバイス行為についても規制対象とすることが適当とした。
価格形成の公正性確保も喫緊の課題だ。暗号資産のインサイダー取引規制について、具体的な規定の導入を検討する一方、「重要事実」や「内部者」の定義など課題も多く、実態に即した規制枠組みの構築には更なる検討が必要とした。欧州や韓国では既に法制化の動きがあり、日本もこの流れに追随する形だ。
ただし、規制強化と並行して、過度な規制によるイノベーション阻害のリスクにも目配りが欠かせない。規制が過重になれば利用者や事業者の海外流出を招き、結果的に国内の競争力低下につながりかねない。Web3やブロックチェーン技術の健全な発展はデジタルエコノミーの進展に不可欠であり、規制と革新のバランスを見極める難しい局面に差し掛かっている。
今後のWeb3時代を見据えると、ノンカストディアル・ウォレットを用いた分散型取引所での取引が増える可能性もある。こうした技術の進化に合わせて規制の在り方も柔軟に見直していく視点が重要だろう。
暗号資産が投資対象として定着しつつある今、利用者保護とイノベーション促進のバランスをどう取るか。コメント募集期間中の議論を通じて、健全な市場発展の道筋を描けるか。日本が暗号資産後進国にならないためにも、実効性ある制度設計が急務である。