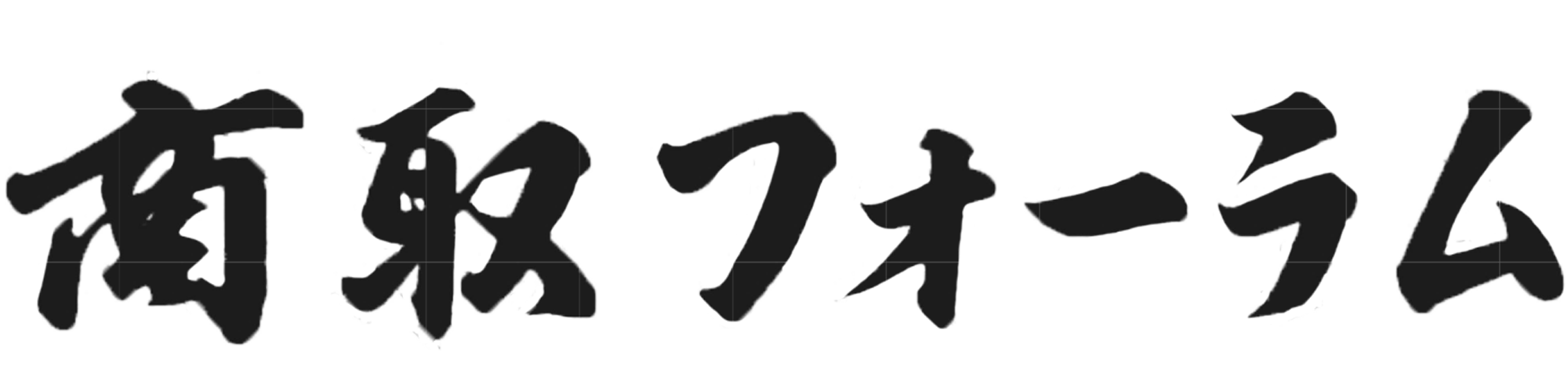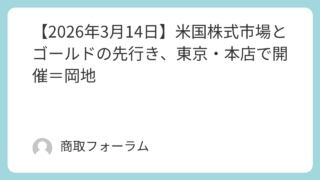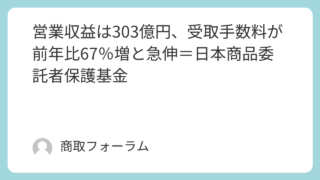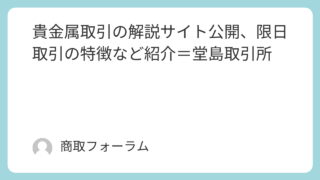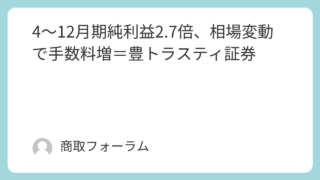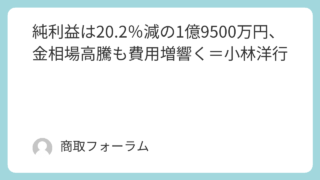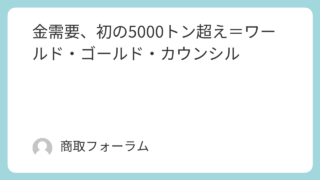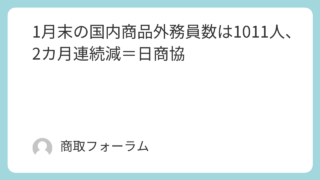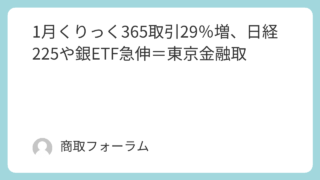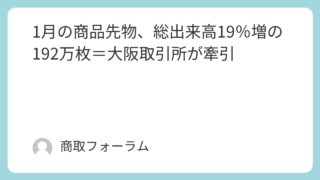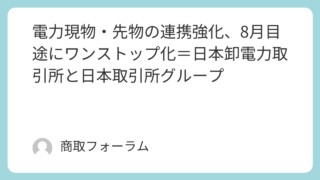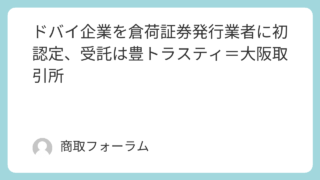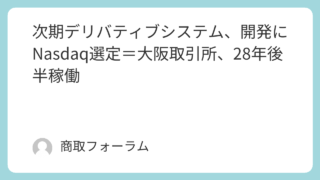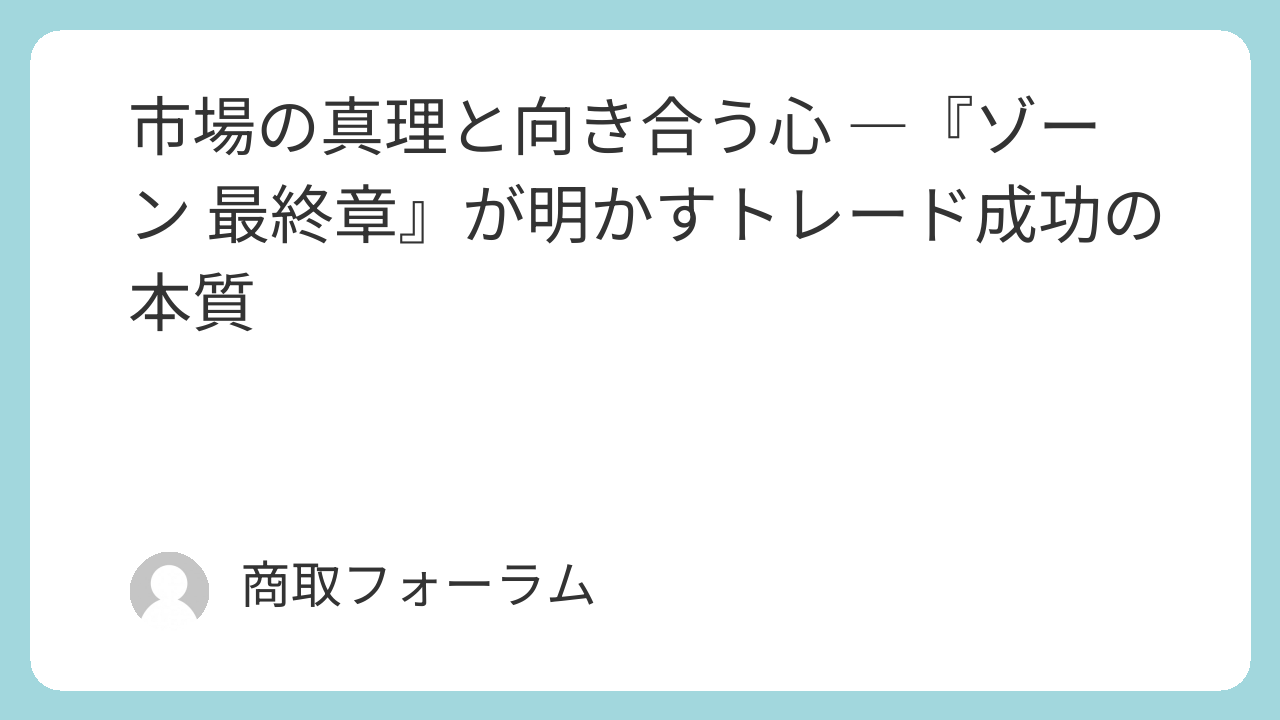『ゾーン 最終章』
金融市場の荒波に揉まれるトレーダーたちが直面する最大の壁は「自分自身」である。チャート分析や経済指標の研究に明け暮れても、なぜ人は感情の揺らぎに翻弄されてしまうのか。この普遍的な問いに真正面から向き合った一冊が、トレード心理学の大家マーク・ダグラスの遺作『ゾーン 最終章』だ。プロ野球選手が絶好調の「ゾーン」状態を求めるように、相場でも無心の境地に至る方法論を説く本書は、投資家の精神修養書として新たな古典となる可能性を秘めている。
心理戦のプロフェッショナルが遺した叡智
シカゴのトレーディング・ビヘイビアー・ダイナミクス社で数多のトレーダーを育成した著者の経験が凝縮されている。従来の投資書が手法解説に終始する中、ダグラスが着目したのは「値動きを生み出す人間心理のメカニズム」だ。市場参加者の欲望と恐怖が織りなすシンフォニーを読み解く鍵として、彼が提唱する「5つの根本的真理」は、現代のアルゴリズム取引が主流となった市場でも色褪せない普遍性を持つ。
証券取引所のフロアで培った臨床観察に基づく指摘は鋭い。例えば「損切りできない心理」を解剖するくだりでは、損失を認めることが自己否定につながるという人間の深層心理にまでメスを入れる。ある読者が語った「負けトレードの後に本書を開くと、自分の過ちが客観視できる」という感想は、まさに著者の意図を体現した証言と言えよう。
確率論という羅針盤
テクニカル分析の限界を説く第3章の論考は目から鱗が落ちる体験だ。ダグラスが強調する「確率思考」の本質は、数学的な期待値計算を超えた哲学的な領域にまで及ぶ。「10回連続で負けても11回目に同じ手法を採用できるか」という問いかけは、トレードシステムの優劣ではなく、トレーダー自身の精神的耐久力こそが成否を分けるという逆説を浮き彫りにする。
ある機関投資家の実例が興味深い。ボラティリティの高い局面で感情的な取引を繰り返していたが、本書の「確率の木」理論を実践した結果、年間収益率が27%改善したという。この具体例は、抽象的に思われがちな心理学の概念が、いかに実践的な武器となり得るかを如実に物語っている。
トレード日誌の革命的な活用法
第11章で詳述される「思考の記録術」は、単なる取引記録を超えた自己分析ツールとして注目を集めている。従来の損益計算中心のジャーナルではなく、意思決定時の感情の起伏まで克明に記録する手法は、認知行動療法の要素を取り入れた画期的なアプローチだ。
ある読者が実践した「怒りのスケール」記録法は示唆に富む。取引中のイライラを0から10段階で評価し続けた結果、特定の数値域を超えると判断精度が急降下する傾向を発見したという。このような定量化された自己観察は、従来の曖昧な感情管理を科学的な次元へ引き上げる突破口となった。
最後のアドバイス
相場と向き合うことは己と対峙する旅である。『ゾーン 最終章』が提供するのは、この孤独な旅路を支える精神的な装備品だ。テクニカル分析の大家ジョン・ボリンジャーが「全てのトレーダーに必要な心理トレーニングマニュアル」と評したように、チャートパターンではなく人間の本質に迫る内容は、時代を超えて輝き続けるだろう。
投資の成否を分ける最後のピースを求めるなら、本書を座右に置くことを勧めたい。ページを繰るごとに、相場と自分を見つめる「第三の眼」が開かれてゆくのを感じるはずだ。まさに現代の『養生訓』とも言うべき、投資家の魂を磨く鏡がここにある。
※リンクはアフィリエイト広告です。お買い物でサイト運営を支援いただけます☕