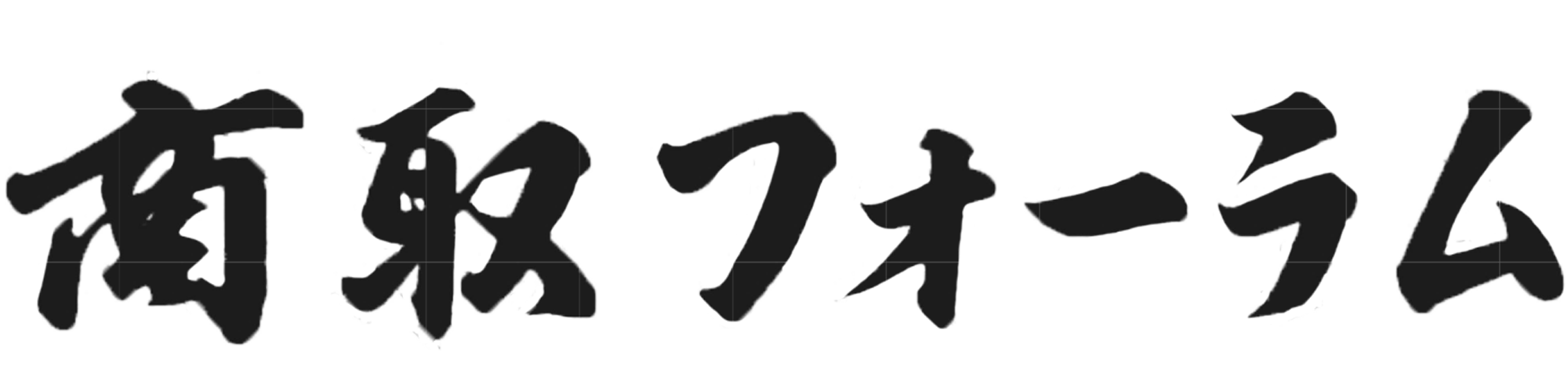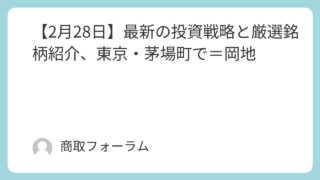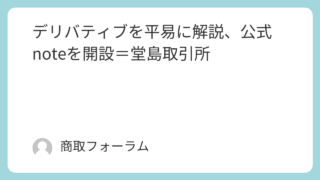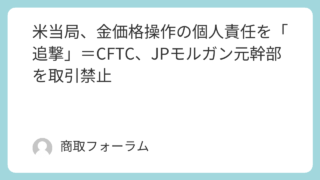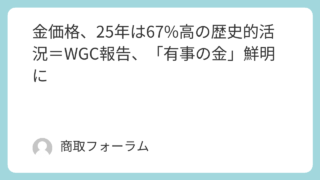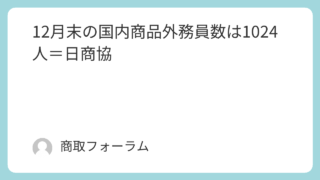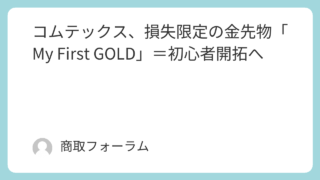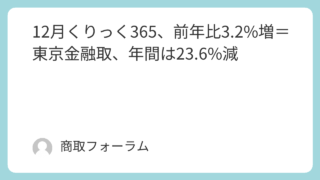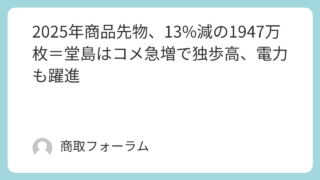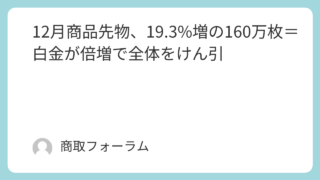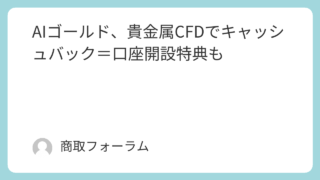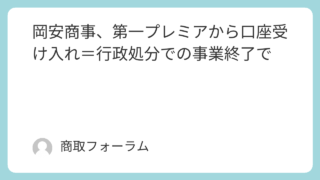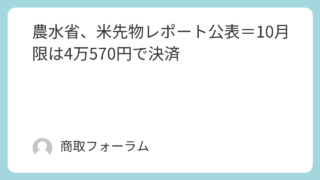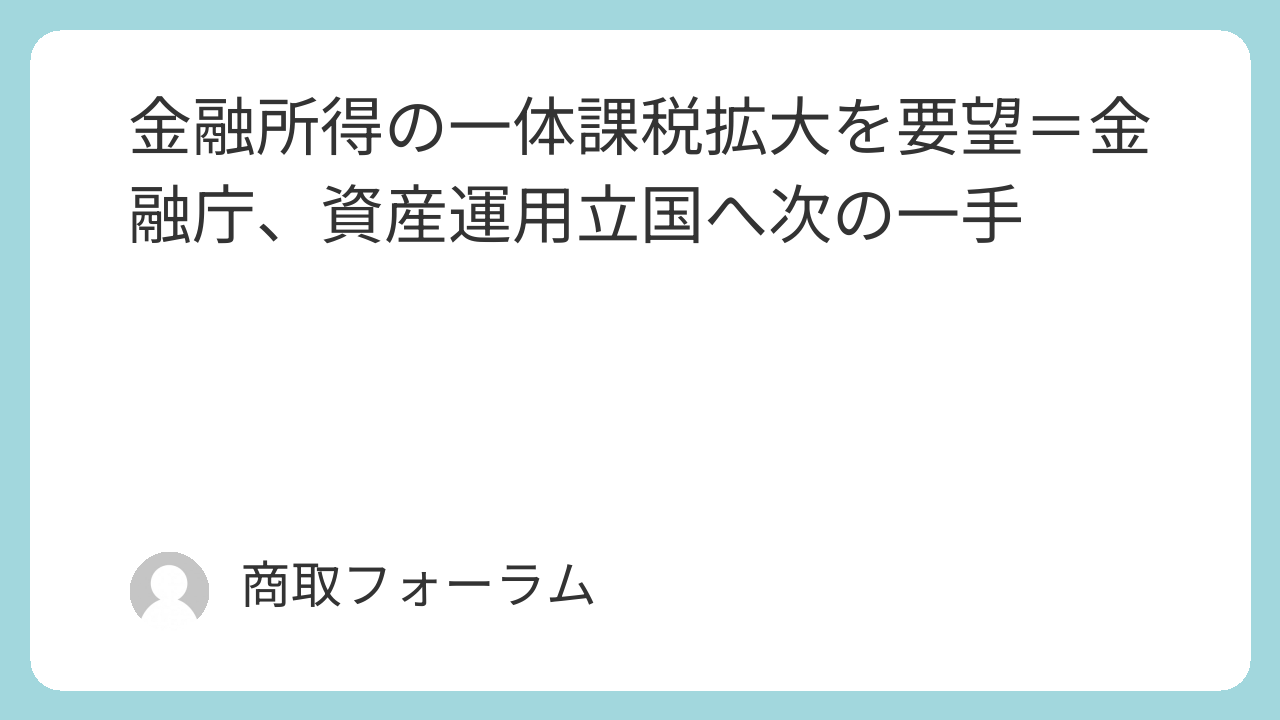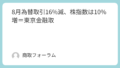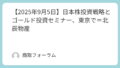金融庁は2026年度税制改正要望で、金融所得課税の一体化を掲げた。デリバティブ取引や預貯金を損益通算の対象に加えるよう求める。家計の多様な資産形成を後押しし、市場への成長資金の供給を促す狙いだ。
金融庁が農林水産省、経済産業省と共同でまとめた要望の柱の一つ。政府が掲げる「資産運用立国」の実現に向け、NISA拡充に続く次の一手と位置づけられる。現在は対象外のデリバティブ取引や預貯金も損益通算できるようにし、投資家がより多様な金融商品を組み合わせやすい環境整備を促す。
特に個人投資家にとって税制上の恩恵は大きい。例えば、保有株式の下落リスクを抑えるためにデリバティブ取引を活用した場合、損失が出ても株式の利益と相殺できる。現状は損失を他の金融商品の利益と通算できず、個人の積極的な活用を妨げる一因とされてきた。改正が実現すれば、個人の投資戦略は一層高度化、多様化する可能性がある。
金融商品の損益通算範囲は2016年に上場株式や公社債などに拡大された経緯がある。しかし、デリバティブ取引などは対象外のままで、課税の一体化は道半ばだった。今回の要望は、残された課題の解決を目指すものだ。
もっとも、実現へのハードルは低いとは言えない。25年度税制改正大綱では「意図的な租税回避行為を防止するための方策」とセットでの検討が求められた。税収減や制度の悪用を懸念する税務当局との調整が不可欠となる。今後、政府・与党内で具体的な制度設計を巡る議論が本格化する見通し。