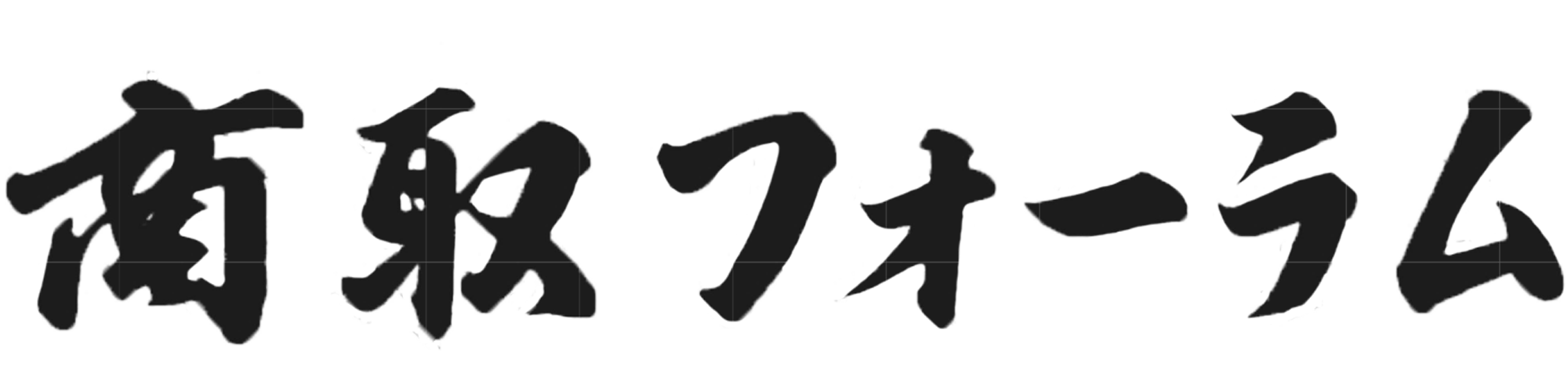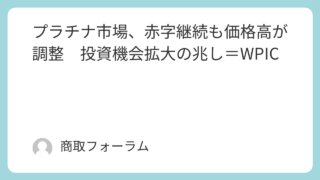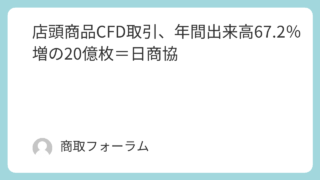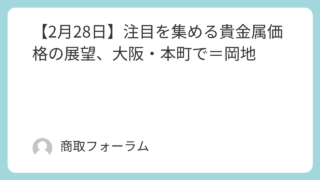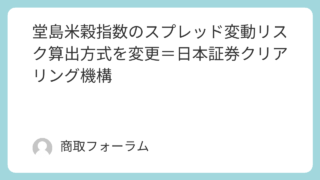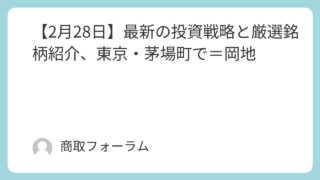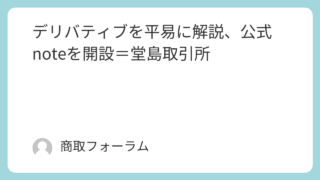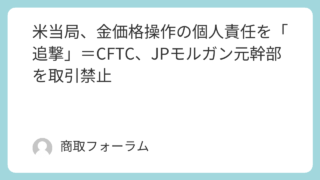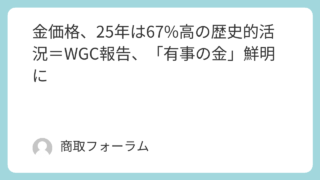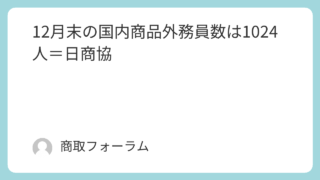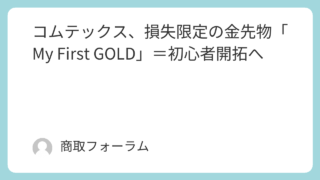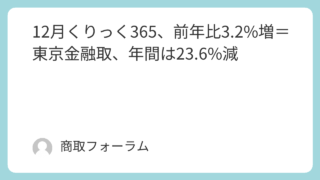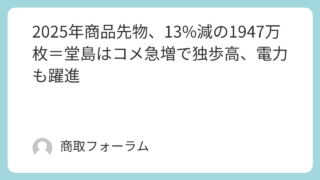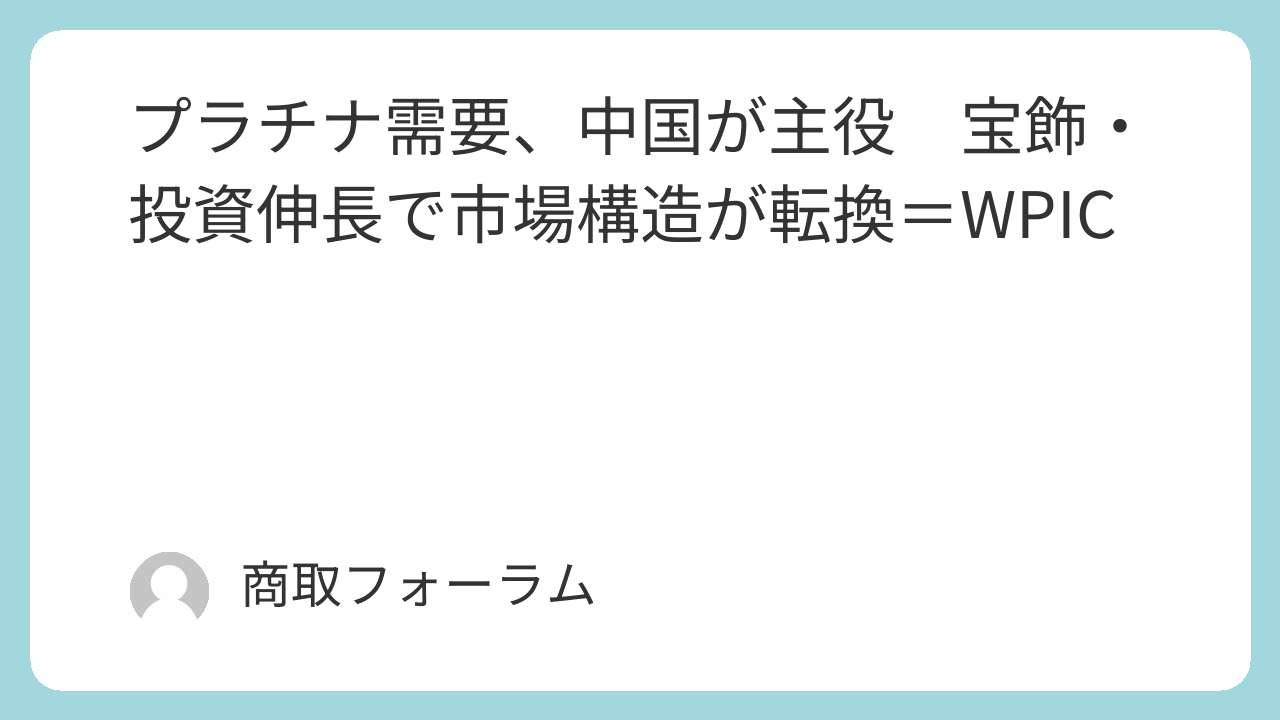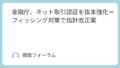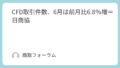ワールド・プラチナム・インベストメント・カウンシル(WPIC)は、2025年の上海プラチナウィークを総括した。中国における投資需要と宝飾需要の急拡大が、世界プラチナ市場の構造を揺るがしている。金価格の高騰を背景にプラチナが割安資産として注目され、従来の自動車・産業用途偏重から脱却しつつある点が今回の報告で明確になった。
金価格の高騰による消費者心理の変化が顕著だ。中国では卸売業者が金で人気のデザインをプラチナで再現する形で商品展開を広げ、現地の中小小売店にも普及している。2024年の投資用プラチナバー・コイン需要は世界の64%を中国が占め、2019年の11%から飛躍的に増加。宝飾需要も小売主導で積み上がっており、今後も投資家・消費者双方の裾野拡大が予想される。
市場に不確実性をもたらしているのが米国による関税政策だが、2025年のプラチナ需要への直接的影響は1.4%にとどまるという。むしろ、投資・宝飾など消費者主導の需要増が全体需給に大きく作用し、供給赤字が2029年まで続く可能性が高まった。今後の経済成長鈍化による産業需要の下押しリスクはあるものの、投資と宝飾が需給を底上げする構図だ。
一方、技術規制と産業構造の変化も注目要素だ。中国の次期排ガス規制「国7」(China VII/7)は2026年に導入され、冷間始動や実走行条件の厳格化で自動車1台あたりのプラチナ族金属搭載量が増加する見通し。塩ビ(PVC)製造業では水銀触媒からプラチナ触媒への完全転換が2030年までに求められ、産業需要の新たな押し上げ要因となる。
さらには水素経済の勃興がプラチナ市場に新局面をもたらしつつある。2030年には世界の電解水素製造容量が100GWへ到達し、その4割がプラチナを用いるPEM型と予測。脱炭素とサステナブル社会への移行という長期潮流も、プラチナ需要の底堅さにつながる。
中国はプラチナ原料の大部分を輸入に依存しており、戦略的備蓄や供給網強化の必要性が今後一層意識されるだろう。逆に言えば、安定供給や市場構造の強靭化を図れば、投資・消費両面で新たな潮流を創出しうるタイミングでもある。
従来の需給構造を覆す潮流の中心に中国がある状況は、他の貴金属や産業素材市場にとっても示唆的である。変動要素は多いが、消費者・投資サイド双方の旺盛な関心が続けば、プラチナ市場は今後も国際的な注目度を保ち続けると評価できる。